スター結線の特徴
この結線方式の最大の特徴は、各相の電圧が線間電圧の1/√3(約0.577倍)になるため、機器の絶縁設計が簡単になることです。また、中性点が利用できるので、三相四線式配電が可能になり、単相負荷にも対応できます。製造現場では、「高電圧の機器を低い電圧で運転できる」というメリットを活かして、大型モーターの始動時の電流を抑える方法としても活用されています。
例えば、自動車工場のプレス機やコンベアシステムでは、スター結線を採用することで、設備の安定稼働と省エネルギー化を同時に実現しています。このように、スター結線は製造業の電力システムを支える重要な技術となっています。
スター結線のメリット
この結線方法は各相の巻線の一端を共通接続点(中性点)に集めて星形に接続するのが特徴です。
「電圧が線間電圧の1/√3になる」という性質があるため、始動時の電流を抑えたい場合に特に有効です。
モーター始動時の電流抑制
スター結線は各相巻線に加わる 相電圧が線間電圧の 1/√3になるため、
大型モーターの直接始動で懸念される突入電流を約 1/3 に低減できます。
実務ではスターデルタ始動として用い、加速後にデルタ結線へ切り替えて定格トルクを確保するのが一般的です。
機器内部配線の簡素化
三相巻線の一端を機内で共通の中性点へまとめられるため、
外部への引き出しは 3 端子(+ 必要なら中性線)のみで済みます。
その結果、端子台が小型化できメンテナンスも容易になります。
ただし外部配線の本数自体はデルタ結線と大きく変わりません。
不平衡負荷に強い電圧バランス
中性線を介して不平衡電流を逃がせるため、相ごとの負荷が多少アンバランスでも相電圧がほぼ定格値に保たれ、機器の発熱や故障リスクを抑えられます。
長時間連続運転や精密装置ではこの安定性が重要視されます。
スター結線とデルタ結線の違い
スター結線とデルタ結線は、三相交流回路で使われる代表的な接続方法です。スター結線(Y結線)は3つの巻線の一端を共通点(中性点)で接続する形で、「星」のような形をしています。一方、デルタ結線(Δ結線)は3つの巻線を三角形に接続する方式です。両者の大きな違いは電圧と電流の関係にあり、同じ電源でもスター結線の方が相電圧が線間電圧の1/√3になるという特徴があります。
変圧器での使用例
変圧器では、一次側と二次側で異なる結線方式を組み合わせることがよくあります。例えば「デルタ-スター結線」の変圧器は、高圧側をデルタ結線、低圧側をスター結線にすることで、効率的な電力変換を実現しています。この組み合わせは配電用変圧器でよく見られ、三相四線式配電に適しています。
モーターでの応用
三相誘導モーターでは、始動時の特性を変えるためにスターデルタ始動方式がよく使われます。最初はスター結線で低電圧・低トルクで始動し、ある程度回転数が上がったらデルタ結線に切り替えて定格運転に移行します。これにより始動電流を抑えつつ、運転時は高トルクを得られるという利点があります。
電力系統での活用
高圧送電線は 3 相導体のみで中性線を持たない場合が多く、発電側巻線は Y 結線(接地)、送電線は実質 Y のまま中性線を省略して運用されます。
変電所では Δ–Y 変圧器 を介して三相四線式 (Y) に変換し、中性線を接地して一般家庭へ配電します。これにより単相 100/200 V 負荷と三相 200 V 負荷を同じ配電線から供給でき、安全性も高まります。

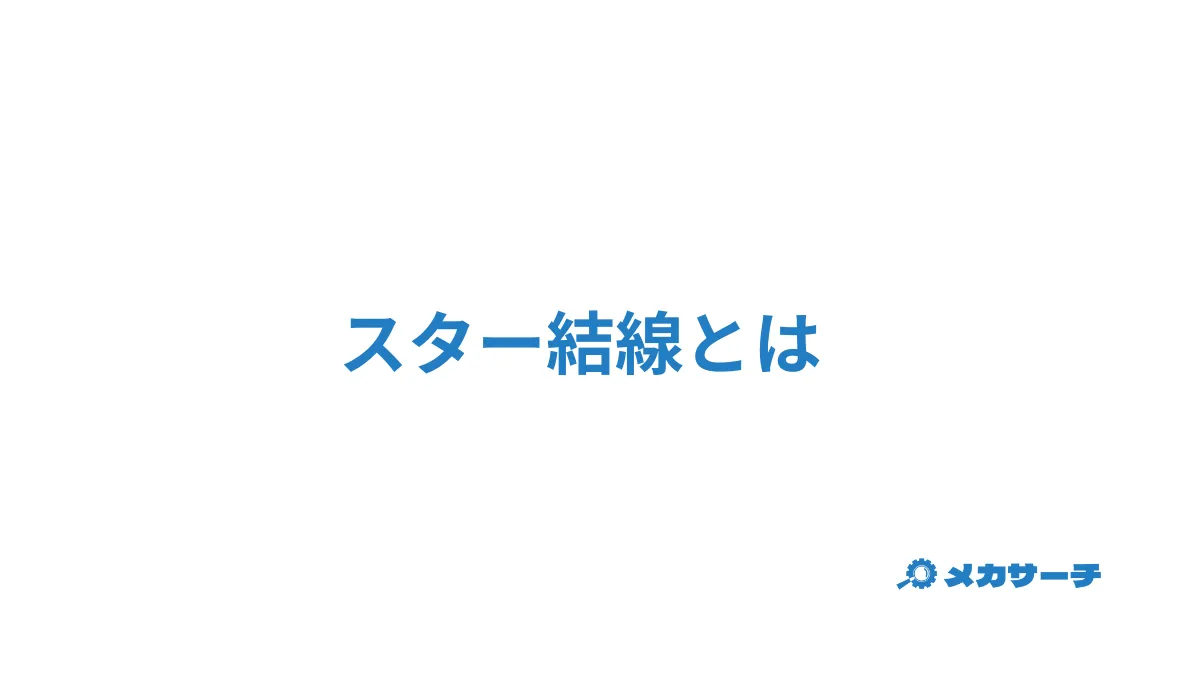

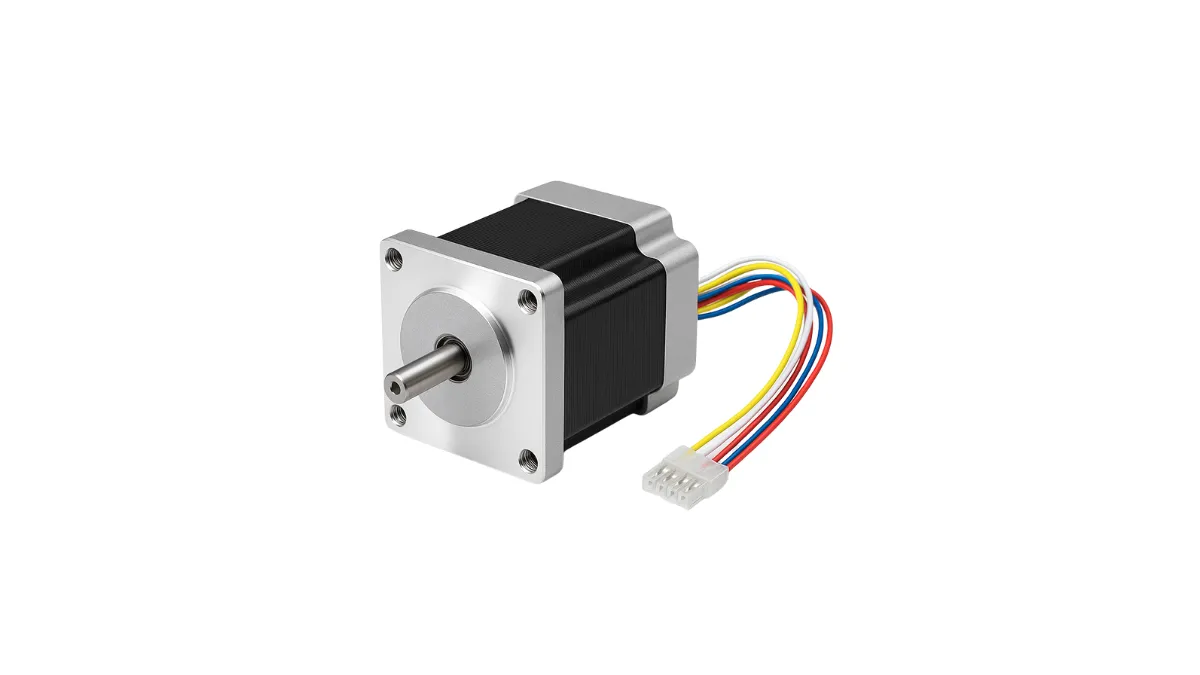





















【監修者コメント】
メカサーチ編集部
メカサーチは、製造業むけ製品・サービス紹介サイトです。専門用語別に製品・サービスの概要やメーカー、製品、専門用語などを紹介しています。