鉄損の求め方
鉄損とは、トランスやモーターなど鉄心(コア)を用いる電気機器で、磁化を繰り返す過程で熱に変換されてしまう電力損失の総称です。主成分は、磁化と消磁を行き来する際に鉄心内部の分子が抵抗に打ち勝って回転する ヒステリシス損と、時々刻々変化する磁束により鉄心内部に誘起される渦状電流が生む 渦電流損の二つです。実務では両者を合わせて「コアロス」と呼ぶこともあります。
これらの損失は経験式であるスタインメッツの式P_{\text{core}} = k\,f^{a}\,B^{b}\quad(\text{W/kg})で近似されます。
周波数を 60 Hz に上げると同条件でもおおよそ 25 % 前後損失が増えるのが一般的です。
実際の機器では、二次側を開放して一次側に定格電圧を印加する無負荷試験(アイドリング試験)を行い、入力電力から温度補正済みの銅損を差し引いて鉄損を求めます。
鉄損と銅損の違い
鉄損は、電気機器の鉄心部分で発生する損失のこと。主に「ヒステリシス損」と「渦電流損」の2種類があります。ヒステリシス損は、鉄心の磁化方向が繰り返し変わることで発生する熱エネルギー。一方、渦電流損は鉄心内に発生する小さな電流(渦電流)によって生じる熱です。鉄損は周波数に比例して増加するので、高周波になればなるほど大きくなる特徴があります。
対して銅損は、コイルなどの導体部分で発生する損失です。電流が流れると導体の抵抗によって熱が発生しますよね。これが銅損の正体です。銅損は電流の2乗に比例するので、電流が2倍になると損失は4倍にもなってしまいます。
実際の数値で見ると、一般的な小型モーターでは全損失の30~40%が鉄損、50~60%が銅損といわれています。省エネ性能の高い電気機器を選ぶときは、これらの損失がどれだけ抑えられているかがポイントになるんですよ。最近のモーターやトランスは、珪素鋼板の採用や導体の太さ・材質の工夫によって、これらの損失を最小限に抑える設計がされています。

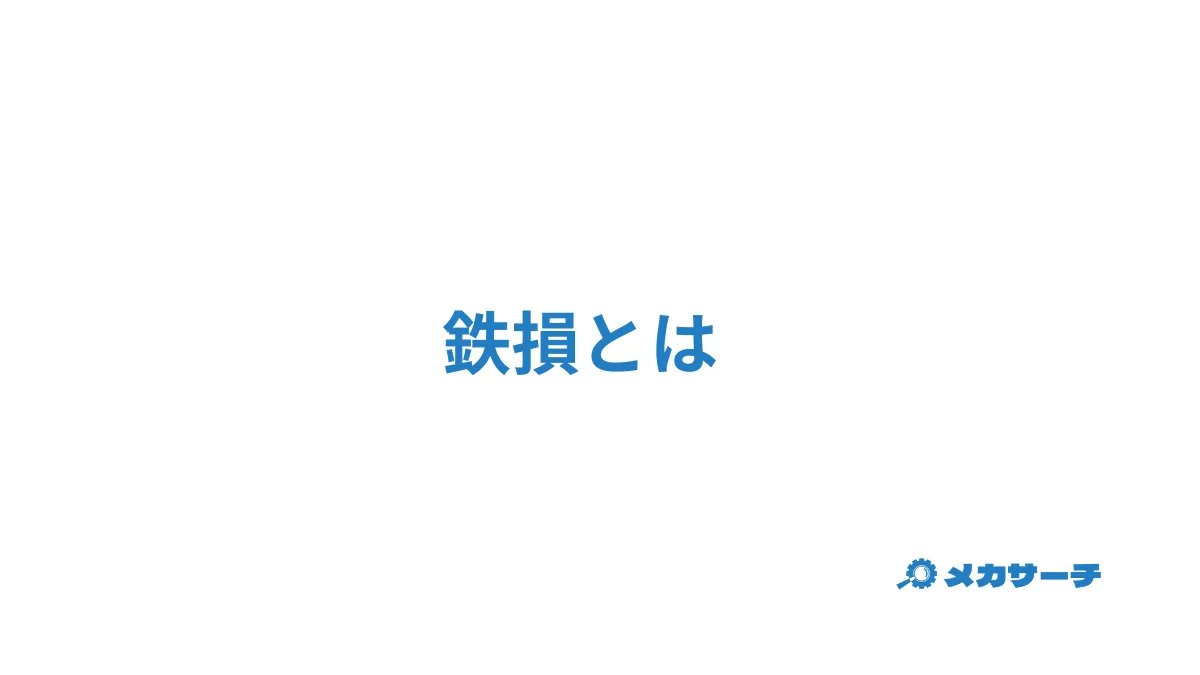























【監修者コメント】
メカサーチ編集部
メカサーチは、製造業むけ製品・サービス紹介サイトです。専門用語別に製品・サービスの概要やメーカー、製品、専門用語などを紹介しています。