力率計算
「力率計算」とは、電気回路における電力の効率を表す重要な指標を求めるための計算方法です。簡単に言うと、供給された電力のうち、実際に仕事として使われた割合を数値化したものなんです。この値が高いほど、電気をムダなく使えていることになります。力率は0から1(または0%から100%)の間の値で表され、理想的には「1(100%)」に近いほど良いとされています。計算式としては「有効電力÷皮相電力」で求められます。有効電力は実際に仕事に変換される電力、皮相電力は供給される見かけの電力のことですね。
例えば、100Vの電圧で5Aの電流が流れている機器があったとします。単純計算すると500VAの電力が供給されているように見えますが、力率が0.8の場合、実際に仕事として使われているのは400W(500VA×0.8)だけということになります。
製造業の現場では、モーターやトランスなどの誘導負荷を多く使用するため、力率が下がりがちです。力率が低いと電気料金が割高になるだけでなく、配電設備に余計な負担がかかってしまいます。そのため、コンデンサーを設置して力率を改善する「力率改善」が一般的に行われています。力率計算は省エネや電気設備の効率化を考える上で欠かせない知識なので、製造現場の管理者はぜひ理解しておきたいポイント!
力率の単位
力率の単位は「%(パーセント)」または「無次元数」で表されます。例えば、力率0.8は80%と同じ意味になります。理想的な状態では力率は1.0(100%)ですが、実際の電気機器ではそこまで高くならないことがほとんど。一般的な工場設備では85〜95%程度が良好な値とされています。
力率が低いとどうなるのでしょうか?例えば力率が0.6(60%)の設備では、供給電力の40%が無駄になっていることになります。これは電気代の無駄遣いになるだけでなく、配電設備に余計な負担をかけることにも。電力会社によっては、力率が低い大口契約者に対して割増料金を請求することもあるんです。逆に力率を改善すれば、同じ仕事をするのに必要な電流が減り、電気代の節約につながります。コンデンサを設置する「力率改善」は、多くの工場で実施されている省エネ対策の一つ。投資コストはかかりますが、長期的に見れば大きな節約になることが多いです。

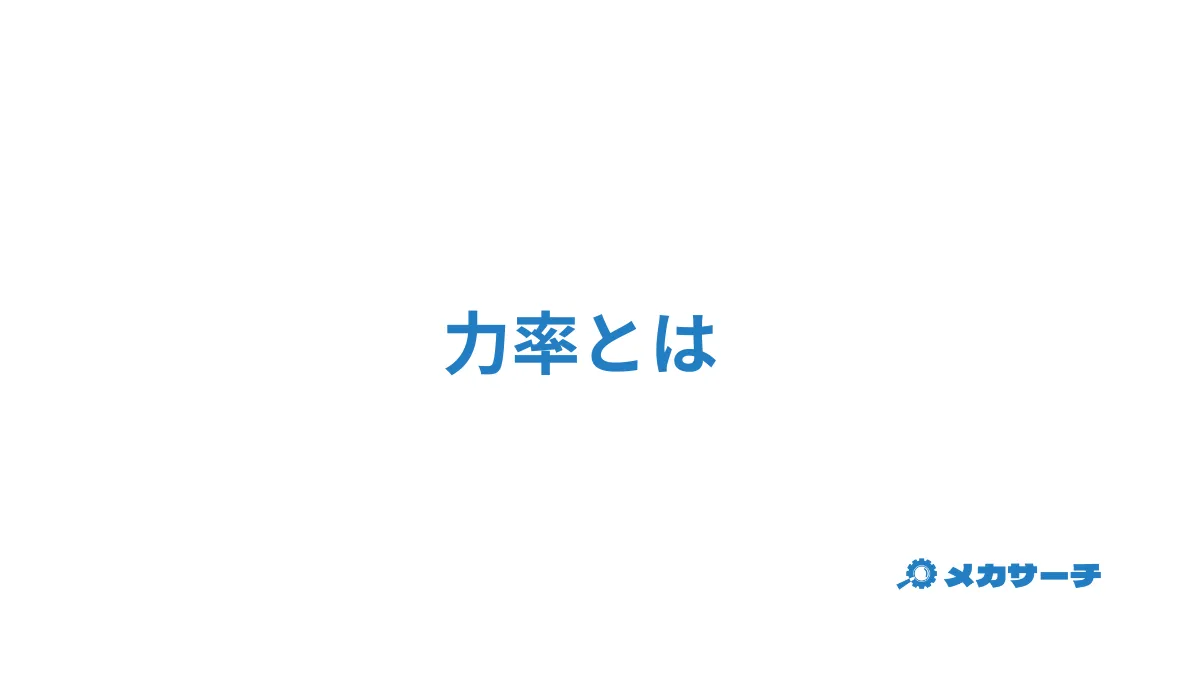

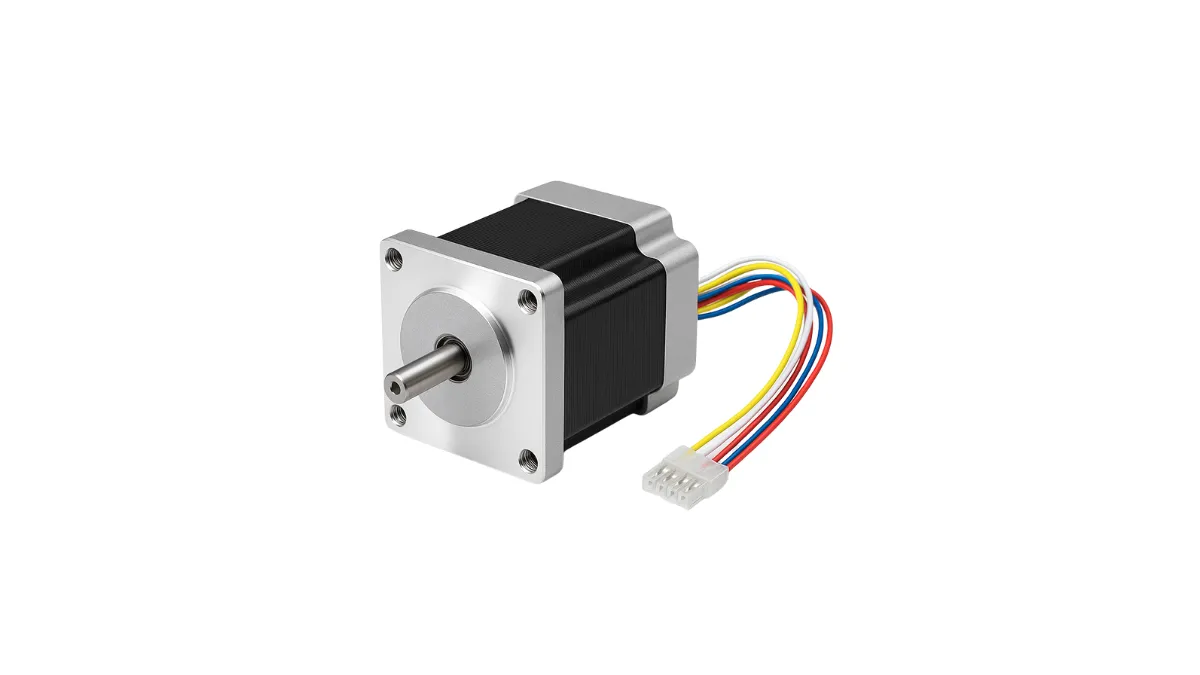





















【監修者コメント】
メカサーチ編集部
メカサーチは、製造業むけ製品・サービス紹介サイトです。専門用語別に製品・サービスの概要やメーカー、製品、専門用語などを紹介しています。